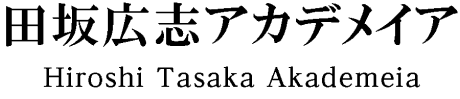メディア
「深き思索、静かな気づき」
No.117
己を磨く 三つの道

筆者は、現在、全国17校、1万人の学生が学び、2千人の教職員が働く学園の学長を務めているが、学生たちと教職員、経営幹部の方々には、「仕事を通じて己を磨く」ことの大切さを伝えている。
では、「己を磨く」とは、いかなることか。
それは、仕事の現場において、年齢を重ねながら「三つの道」での修業を続け、さらなる高みに向かい、成長していくことである。
第一の道は、「腕を磨く」こと。
若い時代の修業は、まず、ここから始まる。
ただし、ここで言う「腕を磨く」とは、「専門的知識」を身につけることや「専門的資格」を取得することではない。「腕を磨く」とは、仕事の経験を通じて、身体的に掴むべき「専門的技能」、すなわち、スキルやセンス、テクニックやノウハウと呼ばれるものを身につけていくことである。
特に、専門的技能を身につけることは、これから極めて重要になる。なぜなら、人工知能(AI)が職場に普及していくこれからの時代には、専門的知識と論理的思考だけで行える仕事は、AIが容易に代替していくからである。そして、その結果、人間が行う高度な仕事は、経験知や身体知に支えられた専門的技能が中心になっていくからである。従って、AI時代には、「学歴」よりも、むしろ「職歴」や「体験歴」こそが重要になっていく。
昔から仕事の世界では「腕に蓄えをせよ」という言葉が語られてきたが、AI時代を迎え、この言葉は、新たな意味で、極めて重要になっていくだろう。
しかし、「腕を磨く」という修業を続けていくと、早晩、次の高みでの修業の大切さに気がつく。
それが第二の道、「言葉を磨く」ことである。
なぜなら、専門的技能を身につけただけでは「良い仕事」ができないからである。
実際、ほとんどの仕事は「チームワーク」を抜きに進められない。そのとき問われるのは、適切なタイミングで適切な言葉を使い、仲間と円滑にコミュニケーションをする能力である。せっかく優れたスキルやテクニックを持ちながら、仕事で壁に突き当たるのは、例外なく、この能力に劣る人材である。
そして、チームリーダーになり、さらに職場のマネジメントを担うようになると、このコミュニケーション力が、ますます重要になる。
リーダーとして、マネジャーとして、能力を発揮できない人材は、ほとんどの場合、コミュニケーションが下手であり、言葉の使い方が稚拙である。
それゆえ、コミュニケーション力を磨くこと、すなわち、「言葉を磨く」ことが、この段階では極めて重要になる。
しかし、「言葉を磨く」という修業を続けていくと、いつか、さらなる高みに向かう道の存在に気がつく。
なぜなら、コミュニケーションの核心は、「言葉」を超えたところにあるからである。
昔から、それを象徴する格言が語られてきた。
「何を語るかではない。誰が語るかだ」
すなわち、第三の道は、「人間」を磨くこと。
リーダーになり、マネジメントの道を歩むようになると、いかに巧みな話術を学び、弁舌爽やかに語っても、部下の心に響かない人物がいることに気がつく。なぜなら、部下が見ているのは、その上司の「言葉」ではなく、上司の人間としての「姿勢」であり、「生き方」だからである。
いや、それは、上司と部下の関係だけではない。顧客や業者との関係においても、それが問われる。
筆者は、若き日に、ある商談で、上司と共に、取引先業者の社長との会合を持ったことがあるが、その社長との会合が終わった後、上司が語った言葉が、いまも心に残っている。
「あの社長は人物だな。この取引、ぜひ進めよう」
尊敬する上司の言葉であったが、当時の未熟な筆者にも、その社長の優れた人間性は伝わってきた。
この「人物」という言葉、最近では死語になっているが、いまも、人生を歩むとき、成長の道を歩むとき、我々が心に刻むべき、大切な言葉であろう。
筆者は、74歳を迎えてなお、いまだ修業中の身、道半ばの身であるが、目の前に聳え立つ「人間成長」という高き山の頂を仰ぎ見るとき、いつも、この言葉が心に浮かんでくる。
人生百年時代。我々は、永き歳月を仕事や職場を変えながら、成長し続けていかなければならない。
その時代に求められるのは、この「仕事を通じて己を磨く」という覚悟であり、いかなる「人間像」を目指して歩むのかという志であろう。