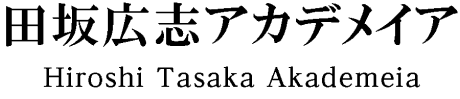メディア
「深き思索、静かな気づき」
No.118
成長する若手 二つの資質

これまで40年余り、実社会において、様々な若手人材の成長を見てきたが、その学びから、将来、大きく成長する若手人材と、成長が壁に突き当たる人材は、かなり明確に予測できるようになった。
では、その判断基準は、何か。
それは、その若手人材が、次の「二つの資質」において、優れているか否かである。
「リズム感」と「バランス感覚」
この二つの資質に優れていれば、その若手人材は、ビジネスの世界で、将来、その能力を大きく開花させていく可能性が高い。逆に、どれほど高学歴であっても、この二つの資質に劣る人材は、残念ながら、よほどの努力をしないかぎり、ビジネスの世界で活躍することはできない。
では、なぜ、ビジネスの世界において、この「リズム感」と「バランス感覚」が重要なのか。
その理由は、ビジネスとは、徹頭徹尾、「人間の心」を相手にする営みだからである。それが、マネジメントにおける上司や部下であっても、商談における顧客や業者であっても、職場における同僚や仲間であっても、いずれ、ビジネスとは、「人間の心」を相手にする営みだからである。
従って、ここで言う「リズム感」とは、自分勝手に好きなリズムで話をしたり、仕事を進めるという意味ではない。それは、相手のリズムに合わせて、こちらの会話や仕事のリズムを変えられる「しなやかさ」のことである。
実際、「リズム感」の悪い人材は、顧客が急いでいるのに、それに合わせて自分のリズムを変えられず、逆に、会議の場などで、周りの気持ちを考えず、自分中心のリズムで会議を進めてしまう。
また、「バランス感覚」も、対人的能力である。
例えば、「営業」では、顧客に商品を買ってもらうためには、ある程度押しが強くないと、成果を出せない。しかし、押しが強すぎると顧客の気持ちが離れてしまう。そのぎりぎりの線を敏感に感じ取りながら、その線を踏み外すことなく商談を進められるのが、優れた「バランス感覚」である。
これは、顧客だけでなく、上司に対して企画を提案するときも同様であり、また、部下に注意・指導するときも、この「バランス感覚」が問われる。
では、どうすれば、我々は、このリズム感とバランス感覚を身につけ、磨くことができるのか。
そのための最も効果的な方法は、リズム感やバランス感覚の良い上司や先輩と一緒に仕事をし、そのしなやかなリズム感や絶妙なバランス感覚を傍らで見て、その呼吸を掴み、体で覚えることである。
昔から「師匠とは、同じ部屋の空気を吸え」という名言があるが、優れた上司からは、ただ傍にいるだけで、この二つの能力を掴むことができる。
筆者は、新入社員の時代、「営業の達人」と評される上司の隣で仕事をしていたが、その上司のリズム感の良い電話応対や、絶妙なバランス感覚の商談交渉に、仕事をしながら、じっと耳を傾けていた。
また、この若手社員の時代、後にこの会社の社長となる専務の海外出張では、しばしば「かばん持ち」を務めたが、この専務からも「同じ部屋の空気を吸う」ことで、実に多くを学ぶことができた。
いま、若手の時代と述べたが、実は、この二つの資質を磨くもう一つの方法は、「失敗」をすることである。例えば、商談で、「ああ、ここまで押すと失敗するのか」という経験を積むと、次第に「ここまで」という線が直観的に分かるようになる。だが「失敗」が許される若手の時代から、それを恐れ、決して踏み込むことをせず、常に無難に仕事に処してきた人材は、しなやかなリズム感も、絶妙のバランス感覚も、決して身につけることはできない。
そして、我々が理解しておくべきは、この二つの資質が、「エゴの問題」と深く結びついていることである。なぜなら、この二つの資質は、「相手の心を細やかに感じ取り、相手の心の動きに合わせることができる能力」だからである。
それゆえ、リズム感やバランス感覚の悪い人材は、表面的には穏やかで謙虚そうな姿を見せていても、実は「エゴ」が固く、心の姿勢が「自分中心」であるため、「相手中心」に考え、振る舞うことが出来ない人材であることが多い。
こう述べると、逆説と思うかもしれないが、人間の表層に囚われない深い心理観察もまた、人間学の要諦であり、マネジメントの叡智に他ならない。