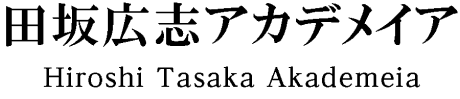メディア
「深き思索、静かな気づき」
No.119
仕事の報酬 五つの意味

仕事の報酬は、仕事だよ…。
筆者が若手社員の時代、上司が語ったこの言葉が、いまも心に残っている。給料は安い会社であったが、その言葉に、なぜか納得したことを覚えている。そして、この記憶が、後に、著書『仕事の報酬とは何か』を書いた理由でもあるが、本論では、その要点を紹介しておこう。
筆者は、我々が日々取り組む仕事には、次の「五つの報酬」があると考えている。
第一は「給料や年収」という報酬であり、第二は「役職や地位」という報酬である。そのため、昔から「この仕事を成功させれば、大幅な昇給だ。そして、部長に昇進だ」などの言葉が語られてきた。
この二つは、誰もが認める「目に見える報酬」であるが、これに加えて、実は、仕事には、「目に見えない報酬」が三つある。
その第一は「仕事の働き甲斐」である。実際、世の中に「給料は安いが、働き甲斐のある仕事」を選ぶ人がいる。その事実が、このことを教えている。
その第二は「職業人としての能力」である。昔から「腕に蓄えをせよ」との言葉があるが、これは、給料が安くとも、腕を磨くことができれば、それがいずれ、様々な財産になることを教える格言である。
そして第三は「人間としての成長」である。筆者は「仕事を通じて己を磨く」という言葉の大切さを語ってきたが、実際、仕事に一生懸命に取り組んでいると、職業人としてだけでなく、一人の人間として成長できたと感じられる瞬間がある。その喜びもまた、素晴らしい報酬に他ならない。
このように、仕事には「目に見える二つの報酬」と「目に見えない三つの報酬」があるが、ここで、もう一つ、我々が理解すべき大切な視点がある。
それは、仕事には「自ら求めて得るべき報酬」と「結果として与えられる報酬」があるとの視点であり、実は、「働き甲斐」「職業的能力」「人間的成長」は前者の報酬であり、「給料や年収」「役職や地位」は後者の報酬である。
筆者が、そう述べる理由は、永年、様々な分野で一流のプロフェッショナルを見てきた結果でもあるが、彼らは、仕事において、何よりも顧客に喜んでもらうこと(働き甲斐)を大切にし、そのために腕を磨くこと(職業的能力)や、人間を磨くこと(人間的成長)を追求してきた。そして、その自然な結果として、仕事での優れた評価が与えられ、高い経済的報酬や社会的地位が与えられてきたのである。
逆に、顧客中心の心を持たず、腕や人間を磨くことをせず、ただ「年収を上げたい」「昇進したい」と考える人材は、その安直な姿勢がゆえに、必ずと言って良いほど、壁に突き当たる姿も見てきた。
このように、仕事においては、何よりも「目に見えない三つの報酬」を求めて歩むべきということが、筆者の「報酬観」であるが、もしこれを理解するならば、我々が、職場のリーダーや企業の経営者になったとき、必ず自らに問うべきことがある。
それは、「自分は、日々の仕事の中で、部下や社員に、この『目に見えない報酬』を、どれほど贈ってるいるだろうか?」との問いであり、深い縁あって共に歩む部下や社員は、「仕事に働き甲斐を感じているだろうか?」「職業人として、腕を磨き、能力を高めているだろうか?」「人間として、精神的に成長しているだろうか?」との問いである。
しかし、この問いを自らに問うならば、自然に、次の三つの問いが、心に浮かんでくる。
「自分は、部下や社員に、仕事の志を本気で語り、働き甲斐を感じられるようにしているだろうか?」
「自分は、部下や社員が腕を磨いたとき、能力を高めたとき、心を込めて褒めているだろうか?」
「自分は、部下や社員に、人間としての成長が喜びであることを、後姿と横顔で伝えているだろうか?」
そして、この問いは、必然的に、さらに深い次の問いに結びついていく。
「自分は、この仕事を通じて、どのような社会貢献をしていくかという、明確な志や使命感を抱いているだろうか? 志を失っていないだろうか?」
「自分は、部下や社員が褒められて喜ぶような、高度な職業的能力を身につけているだろうか?」
「自分は、何歳になっても、人間として成長し続けているだろうか? 成長を忘れていないだろうか?」
この三つの問いは、いずれも厳しい問い。しかし、その厳しさから逃げることなく、この問いに正対したとき、日々の職場の風景が全く変わって見えてくる。
そして、そのとき、我々は、リーダーとして、経営者として、さらなる高みに向かっている。